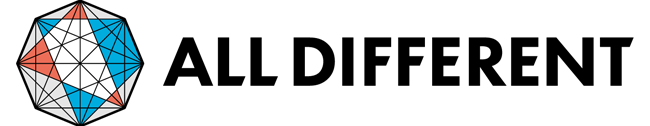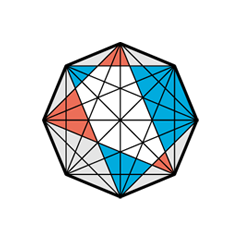チームビルディングとは?成果を出す組織の必須スキル!
 更新日:2022.05.24
更新日:2022.05.24
 公開日:2019.07.02
公開日:2019.07.02

また、メンバー間で目的を共有できている、主体的な働き方をしているなど、いろいろな特長があげられると思います。
このような組織を作り上げるうえで重要になる施策のひとつに「チームビルディング」があります。
本コラムではチームビルディングの概要や著名なフレームワークを活用した実践のポイントについてお伝えします。
チームビルディングとは
チームビルディングとは、目的達成のために複数人が集まり、一人ひとりの能力を活かす組織をつくるための取り組みのことです。似ている言葉に「チームワーク」がありますが、どのような違いがあるでしょうか。
チームビルディングとチームワークの違い
ビジネスにおいての「チームビルディング」と「チームワーク」は、目標の方向性が異なっています。
チームワークの”ワーク”は、「仕事やタスク」という意味になります。そのため、企業全体で取り組むというよりは、部署や部門、あるいは各部署からの代表者の集まりなど、小規模単位の従業員が力を合わせ、効率的にタスク業務を行うことを意味します。チームワークは、あらかじめタスク(仕事)の全体像が見えていることが前提です。
一方、チームビルディングは個人個人のスキルや能力・経験などの強みを持ち寄り、”目標達成”を目指すための取り組みを意味します。この目標とは、特定のタスクを解決するのではなく、企業全体で掲げている経営ビジョンの実現を目指すものです。企業経営を高めるために、異なるスキルを尊重し合って融合させ、付加価値や生産性を高めていく試みがチームビルディングです。
チームビルディングを行う目的
チームの力を最大化させて経営ビジョンを達成するためには、チームが一丸となって、同じ目標に向かって進んでいける組織づくりが重要となります。
近年、グローバル化・多様性の時代と言われ、国籍問わずさまざまなバックボーンの人材とともに働く機会が増えています。また、フレックスタイム制やリモートワークなど、柔軟な働き方が一般化しつつあります。こうした環境の中、チームとして掲げられた目標を達成し、成果を最大化するためには、日本特有の「あうんの呼吸」や「察しと思いやり」といった文化は通用しません。チームが一丸となって同じ目標に向かって進んでいける組織づくりの取り組み、すなわち「チームビルディング」が重要となるのです。
こちらでは、チームビルディングを実施する具体的な目的を幾つか紹介していきます。
コミュニケーションを活性化させるため
チームビルディングを行う目的の1つが、コミュニケーションの活性化です。メンバー同士が、お互いの意見や情報を共有しながらコミュニケーションを深めることで信頼関係を構築でき、建設的な意見交換が行えます。
チームビルディングを始めたばかりの段階では、個々の能力はあっても連携がとれておらず、チームとしての力を発揮するには至っていないでしょう。コミュニケーションを活性化させることで、お互いの理解が進み、それぞれの得手不得手を鑑みたチーム運営が可能になります。
能力に合った適切な人材配置を行うため
チームビルディングの大目的は、組織としての目標達成にあります。そのためには、チームメンバーの能力が最大限に発揮できるようにしなくてはいけません。
適切なコミュニケーションを取ることで、メンバーの持つスキルや知識を把握しやすくなります。その情報をもとに人材を配置すれば、仕事の効率化が図れ、役割が明確になるでしょう。
逆に、スキル不足の社員がいた場合でも、どこに配置すればより成長を見込めるかも考えることができます。
マインドセットの形成を促すため
マインドセットとは、これまでの教育や経験などから形成される思考パターンや物事の見方を指す言葉です。「無意識の思考のクセ」や「思い込み」と言い換えることもできます。
チームビルディングにおいては、企業の組織的ビジョン達成のために、新たなマインドセットを形成する必要があります。
ビジネスにおいて、マインドセットを形成するにはいくつかの方法があります。例えば、ゲーム性を持たせたアクティビティを実施し、メンバー同士が能動的にコミュニケーションを取るように促せば、チームの結束力が高まり「目標達成に前向きに動こう」とするマインドセットが形成できます。
チームビルディングを成功させるために必要なこと
チームビルディングはリーダーシップを発揮するための1つの「要素」とも言えますが、リーダーシップを発揮した結果得られる「成果」とも考えられます。
「成果」としてチームビルディングをとらえると、その推進にあたっては当然リーダーシップを発揮できるような「資質」が管理職に求められます。ここでは、代表的な3つの資質についてご紹介します。
(1)ビジョニング
チームビルディングにおいては「ベクトル」や「プロセス」が重要な要素です。これを実現させるため、管理職は会社のビジョンや戦略をもとに「将来のあるべき姿」を明確に描く必要があります。
また、このあるべき姿を踏まえ、具体的な達成目標へと落とし込み、どのようにその目標を達成していくかの方針を示すことも求められます。こうしたビジョンを描くことを「ビジョニング」と呼びます。リーダーに求められる役割であり、必要な資質と言えます。
(2)コミュニケーション
チームの活力を高めるためには円滑なコミュニケーションを育む環境が不可欠です。(1)でご説明したビジョニングを実現させるためにも、いかにチーム全体に浸透させられるか、という点においてはコミュニケーションが重要になります。チーム全体の空気を形作るために、管理職には高いコミュニケーション能力が求められるのです。
(3)意思決定
リーダーの仕事は「意思決定をすること」です。自分自身の業務だけでなく、チームの運営や他部門間の調整、メンバーの育成、評価など判断が求められるシーンは多岐に渡ります。1つの判断が多くのメンバーに影響を与える可能性があるため、意思決定にあたっては高い情報収集能力と、全体最適の視点が欠かせません。
このようなスキルを持ち、公平・明確な判断基準で意思決定することができれば、メンバーからの信頼を勝ち得ることができ、チームビルディングにおいても大きな追い風となります。
チームビルディング4つのステップ
実際にチームビルディングを進めるにあたって、チームがどのようなステップを経て成熟していくのかを理解しておきましょう。 著名なフレームワークとして、アメリカの心理学者である、Bruce Tuckman氏が考案した「タックマンモデル」を紹介します。 タックマンモデルでは、チームビルディングを形成期・混乱期・統一期・機能期の4つのステップで整理しています(散会期を含めて5つとする向きもあります)。
<チームのパフォーマンス>
ステップ(1):形成期
形成期は、チームを構成するメンバーが決定したばかりの段階であり、まだメンバーはお互いのことをあまりよく知らず、チームのビジョンや目的といった内容も理解していない状態です。
このステップにおいて重要なことは、リーダーがチームのビジョンを明確に示し、メンバーへの浸透を促すことです。
同時にメンバー間の理解を深めるため、コミュニケーションを密にとれる場を提供することも必要になります。
形成期における具体的な手法
初対面、もしくは仕事上で関わる機会の少ないメンバー同士を組み合わせてチームを作り、ペアインタビューを行います。
ペアインタビューは、相互理解を深めるためのワークショップ手法の1つで、2~3名の少人数グループを組み、特定のテーマについて聞き手と話し手(3名の場合はオブザーバーも含める)を交互に担当します。
インタビュー後には互いに感想を伝え合い、より深い理解促進を図ります。
ステップ(2):混乱期
混乱期は、チームのビジョンや目的が明確になった後、どのようにその目標を達成するか、解決方法を模索する段階を指します。
このステップにおいては、チームの動き方を検討するため、各メンバーの考え方や仕事の進め方について衝突が起きることも想定されます。しかし、この段階で意見の衝突を避け、リーダーや発言力のあるメンバーに迎合してしまうと、メンバー同士の不満や不信感が蓄積してしまい、後々チームとしての活動に深刻な影響を与える可能性もあります。
メンバーの相互理解を深めるためにも、率直な意見を出しあい、しっかりと議論することが重要です。
混乱期における具体的な手法
疑似的に体験する機会を通じて、混乱期における立ち居振る舞いを認識させる体感型のワークショップを2回以上実施します。(例えばペーパータワー、レゴゲームなど)
1回目のワークでは、チーム内の役割分担を特に指示せず、ワークを実施します。多くの場合では、それぞれが思い思いに動いてしまい、チームとしての一体感やまとまりが生まれず、失敗してしまうと思います。そのうえで、2回目のワークに臨むことで、1回目の失敗を受けてどのように役割分担してワークに取り組むべきかを各チームが考える機会を提供します。
そうすると1回目よりもよい成果が得られ、役割分担の重要性など、混乱期を乗り越えるために必要となるポイントの理解が促進されます。
ステップ(3):統一期
統一期は、チームとしての行動規範や役割分担が形成される段階を指します。
混乱期をともに乗り越える経験を経て、チームとしての団結が強まり、徐々にチームとしての機能が発揮される段階を迎えます。個々人が発言をしても、衝突する問題はなく、活発に議論が進みます。
重要なことは、間違った方向に進まないように、リーダーが必要なときに軌道修正を行うことが重要です。
ステップ(4):機能期
機能期は、チームとして機能し、成果を創出する段階を指します。
統一期の時点でチームとしての成果は上がり始めるのですが、その状態を継続するためには状況にあわせて活動方針や役割分担の見直しや調整が必要になることもあります。この段階では、PDCAサイクルを回してチームの生み出す成果を維持・増化できるよう努めることが求められます。
チームを上手く機能させる5つのポイント
チームビルディングをスムーズに進めるために押さえておきたい5つのポイントについて解説します。
1.必要な情報をきちんと共有する
1つめのポイントは、チームを円滑に機能させるために必要な情報をメンバーに共有することです。
リーダーや特定のメンバーだけが情報を抱え込むと、他のメンバーが次の行動に移せなかったり、誤った方向へ進んでしまったりと、効率や生産性が低下する可能性があります。
細かい情報はもちろん、最終目標のゴールへ向けての計画や進捗状況、課題などはチーム全体で情報を共有しましょう。
2.目的意識を持ってもらえるようにする
2つめのポイントは、目的意識を持ってもらえるようにすることです。目的や目標がわからないと、メンバーは困惑してしまうでしょう。具体的に、どのように目標を設定すればよいかは、下記を参考にしてみてください。
【目標を達成するための設定例】
- ● 第三者から見てもわかりやすい「具体的」な目標設定
- ● 目標の達成度がわかりやすい「定量的」な設定
- ● 達成することができる「現実的な設定」であること
- ● チームの「ビジョンに関連」している設定であること
- ● 目標を達成するまでの「期限を設置」する
これは、SMARTの法則というフレームワークです。目標設定を考える際は、フレームワークを活用するのもよいでしょう。
チームリーダーはメンバー各自の目標管理を行い、業務の遂行具合を把握してください。メンバーからの相談やサポートに応じることで、モチベーションの維持やチームの一体感が生まれ、生産性の向上につながります。
3.個々の役割を明確にする
チームの機能性を高める3つめのポイントは、メンバーひとり一人の役割を明確にすることです。
役割を設定する際、チームリーダーは、個々の得手不得手を把握することからスタートします。本人の希望も加味したうえで役割を与えましょう。得意なジャンルと本人の要望に基づいて与えた役割は、当事者意識の醸成にも役立ちます。
ただし、このように決定した役割分担は、案件によっては業務量の差を生み出してしまうこともあります。
そのような場合は、お互いにサポートし合うよう、事前にメンバーへ周知しておくのも大切です。
4.メンバーの自主性や自律性を重んじる
メンバーの自主性や自律性を尊重する環境も、チームを上手く機能させるポイントのひとつです。
コロナ禍以降、テレワークが浸透しているなか、各自の判断でやるべきことを見極めて目標に向かって行動できる自主性や自律性のある人材が求められています。リーダーは、課題を解決する方法を指示するだけでなく、メンバー自身に考えさせ、判断させる裁量を与えることも大切です。
そして、もしビジョンや目的から外れた行動を起こしたメンバーがいても、頭ごなしに否定はせず、どのようにすればズレが生じなかったのかを指導しましょう。
5.心理的安全性を高める
心理的安全性とは、「psychological safety」を和訳したもので、組織やチーム内で安心して自分の意見を発言できる”風通しのよい”状態を指します。
この心理的安全性の基盤を作るのが、チーム内でのコミュニケーション量です。コミュニケーションが多い環境ほど、相互間の違いや多様性があることを認め合い、お互いの理解を深めて本音を言いやすい場を作れます。
この心理的安全性の基盤を作るのが、チーム内でのコミュニケーション量です。コミュニケーションが多い環境ほど、相互間の違いや多様性があることを認め合い、お互いの理解を深めて本音を言いやすい場を作れます。
立場や対人関係を心配せず、発言した分だけチームの雰囲気が活性化するので、業務に対するエンゲージメントが高くなり、モチベーションも上がります。
メンバーひとり一人のパフォーマンスが向上すれば、チームや組織全体の業績アップも期待できるようになります。
チームビルディングを行う際の注意点
チームビルディングを行う際に、注意したいポイントがあります。
チームビルティングを成功に導くためには、次にあげる3点に注意して実施していきましょう。
無理のある目標設定にしない
チームビルディングを実行する際、無理な目標や強制的な目標は、メンバーのモチベーションを低下させる恐れがあります。強制的な目標は「上司からの命令でやらされている」と士気が下がるおそれがあり、現実離れした目標は「非現実的な夢物語」になりがちです。そうなると、目標としての意味を失ってしまいます。
メンバー放任主義はNG
メンバーひとり一人の自主性や主体性を重んじることは、チームビルディング成功のために必要な要素ですが、自由度を高くしすぎた放任主義はNGです。節目ごとのフィードバックやアドバイスを怠り、すべてをメンバーに丸投げした状態では、チームは方向性を失い結束力を弱めてしまう恐れがあります。
チームリーダーは、目標と行動にずれがないか常に方向性を示し、チームとしてしっかりと機能しているかを確認しながらメンバーをまとめていきましょう。
親睦を深めるグループワークが単なる遊びにならないようにする
チームビルディングの初期段階(形成期)では、メンバー間のコミュニケーションを図るためにアイスブレイクを導入することがあります。
アイスブレイクとは、その名前が示す通り、心や体、その場の緊張を解きほぐすためのアクティビティのことです。
自己紹介をはじめ、場が和むゲームやグループワークを行うことで、メンバーの緊張を解き、安心感を与えます。
しかし、この親睦を深めるためのグループワークが、単なる遊びになってしまっては意味がありません。
単に「楽しかった」で済まされないように、グループワークの目的を予めメンバーに伝えてからスタートしましょう。
チームビルディングが必要となるシーン
(1)小売業におけるチームビルディング
小売店や販売店では、正社員、主婦のパートタイマー、学生アルバイトなどさまざまな雇用形態、幅広い年齢の従業員とともに、日々の売り上げ目標の達成を目指して店舗運営していく必要があります。個人ごとの売り上げ目標を追求するあまり、メンバー間で衝突が発生することもあるかもしれません。
店長やエリアマネージャーのようなリーダーは、売り上げ目標という成果を達成するために、チームとしての一体感を高め、円滑なコミュニケーションが生まれる環境づくりに力を割いていく必要があります。
(2)IT業におけるチームビルディング
システム開発等プロジェクトで業務を進める機会の多いIT業においては、多彩なスキルを持つメンバーをまとめながらプロジェクトを進行するPM(プロジェクトマネジャー)としての能力が問われます。
各々のスキルセットを把握し、適材適所のアサインを行い、納期通りに期待以上のクオリティの成果物を形作るためには、一枚岩になり、しっかり噛み合ったチームづくりが重要です。
(3)新規事業におけるチームビルディング
不確実性の高い新規事業では、既存のベストプラクティスをそのまま流用していてもなかなかうまく進まないことも多いでしょう。セオリーがないからこそ、リーダーひとりの考えに固執せず、メンバーから多彩な意見を拾い上げることが求められます。
自由闊達な議論を行いやすい空気を作ること、メンバーがいきいきとプロジェクトに取り組める環境を用意することが新規事業成功のカギになります。
これらのシーンに共通していることは、チームとして掲げられた目標を達成するための手段として、メンバー間のコミュニケーションを円滑にする「空気づくり」が重要であり、それを能動的に生み出していく動きがチームリーダーに求められるということです。
グループからチームに進化させよう
グループとは、個人が集まり一緒に仕事をする人々の集団のことです。互いにコミュニケーションや関連はあるものの、それぞれ個人的な目標に向かって仕事をしている状態です。そして、チームビルディングは、このグループの状態から共通のビジョンや目標を達成するためにサポートし合う「チーム」へ進化させる取り組みです。
メンバーの「個人力」が優れていたとしても、目指す方向性がバラバラで、コミュニケーションが不十分では、ポテンシャルを発揮することはできません。しかし、チームが一丸となって同じ目標に向かって進む組織は、最大のパフォーマンスを生み出すことが可能です。
特に、フレックスタイム制やリモートワークなど柔軟な働き方へと移行している現在、生産性を担保する観点からも、チームビルディングの重要性はますます高まっています。
チームビルディングを成功させるには、チームを指導してまとめられるビジネスリーダーや管理職の育成が必要不可欠です。社内研修などを実施して、後輩への指導術やチームビルディング研修などに力を注ぎましょう。